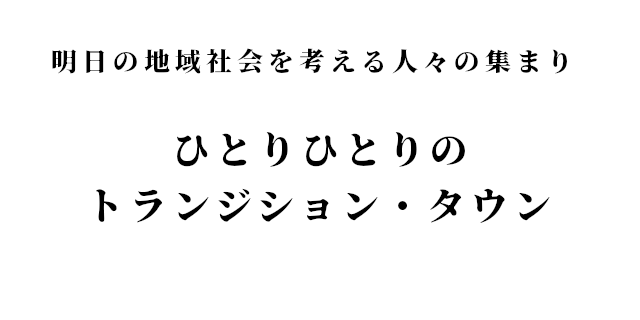2015年に発行された『共生の「くに」を目指して』(赤堀 芳和著)では、日本において国民のための国家がなぜ成立し難いのかということで、幾つかの考え方が示されています。
例えば、国による国民世論の操作、政治に民意が反映されていないなどの点です。 これらの点については、理解の程度に差はあるにしても、私たちの多くが感じていることではないでしょうか。 ただ、勘違いしてはならないことは、「国」という実体は存在しない(概念上の空間)という点です。 つまり 国 →政治家が活動するための「場 」であり、私たちが生きるために必要とする実体としての「場」(物理的な空間)とは異なります。
ここで、少し考えてみてください。 あなたは今、あるテーマについて話しをするために、多くの人の前に立っているとします。 進行役の方があなたのプロフィールを紹介した後で、あなたはゆっくりと話しはじめます。 その後の聴衆の様子は、進行役の方が口にした、ただ一言により大きく変わる可能性があります。 たとえあなたが全く同じ内容の話をしたとしても、進行役の方があなたをXXX機関の主任研究員と紹介すれば、聴衆には学術的な研究の話のように聞こえるでしょうし、〇〇〇NPO法人の地域支援グループリーダーと紹介すれば、社会的な活動の話のように聞こえるでしょう。
これは、別の意味で威光暗示効果的な働きによるものではないかと思いますが、私は「入れ物(表象)」と「中身(実体)」の関係を比喩的に良く用います。 具体的には、ラベルを剥がしたペットボトルにある液体を入れて、その液体が一体何かを考えるというものです。 ただし、ペットボトルに触れることはできません(ペットボトルの蓋を開けて匂いを嗅いだり、ペットボトルを振ったりすることはできません)。
つまり、「国民のための国家がなぜ成立し難いのか」といったことの理由の一つに、上記に上げた比喩があるのではないかということです。 もちろん、他にも重要な問題は多いと思いますが、ここからは一度原点に戻って、「入れ物+ラベル(看板)= 表象」と「中身(実体)」の関係について考え直してみたいと思います。