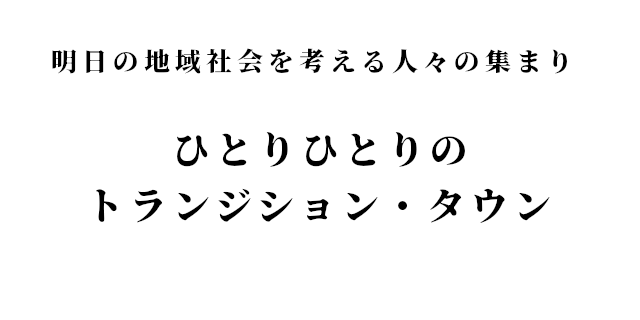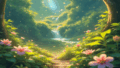JIU 市民未来大学 ヘルスプランナーコース 5月2日は「フレイル概論」でした。
1年次にもフレイルという言葉は聞いていましたが、 それは他の教科(例えばヘルスプロモーションや地域包括ケアシステム)の中で使われたものでした。
今回の授業では、「フレイル(虚弱)」という言葉の概要を知り、それが他の教科とどのような関連性を持つのかを学びました。 先の授業(老年学)で学んだように、老化の個別領域の知見を踏まえつつ、それらの相互の関連性を理解することが重要な点になると思いますから、授業の流れとして上手く組み立てられていると感じました。
それと同時に、(いつものことではありますが)今まで気付かなかった(あるいはモヤモヤしていた)新しい疑問や考え方が芽生えます。
老年学でも触れられていましたが、老化の原因の一つに「テロメア」説があります。 真核生物(膜に包まれた核と呼ばれる構造をもつもの)のDNAは線状で両端をもつため、細胞を複製する際に原理的な問題が生じます。 それは、一番端まで複写することができないようになっているので、細胞を複製する度にDNAの両端(この部分がテロメア)が欠けていく(短くなる)というものです。
テロメア自体に遺伝情報が記録されているわけではないようなので、多少短くなっただけでは問題はないと思いますが、この部分が短くなり過ぎると、細胞は複製できずに死を迎えるとされています。
ここまでは、一般に広く知られていることではないかと思いますが、じつは生殖細胞ではテロメアーゼという酵素が働いて、テロメアの長さを調節することが知られているそうです。 また比較対象として、真正細菌(大腸菌や乳酸菌などのバクテリア)のDNAは一本の環状DNAが基本(近年のゲノム解析により一部の例外が報告されている)なので、真核生物に見られるような複製時の問題はないということです。
老化が遺伝子により制御されているものならば、生物としての終焉を即座に終わらせることなく、フレイル(プリフレイル→フレイル)→要介護(身体機能障害)→天寿(死)といった段階を踏むのは何故でしょうか?