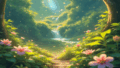Wikipediaでは、
『平衡(へいこう、英: balance, equilibration, equilibrium)は、物が釣り合って安定していること、あるいはその釣り合い。 平衡させることを英語で equilibrate といい、そのときの状況が equilibrium である。 balance および equilibrium は「平衡」の他に「均衡」とも訳される』
と説明されています。
ここで、なぜ「平衡」という言葉を持ち出したのか、疑問に思う方がいらっしゃるかも知れません。
じつは、図書館で何気なく手に取った本に「動的平衡」という言葉があり、調べてみたところ、
『動的平衡とは、生物や生態系が、絶えず変化しながらも全体として一定の状態を保つ状態のことです。一見すると静止しているように見えても、内部では常に分解と合成、あるいは変化と再構成が繰り返されている状態を指します』
と説明されていました。 そう言えば、以前に「人工生命」に興味を持ち、読み込んだ本の中に確か「動的平衡」という言葉が出ていたように思います。
このとき、なんとなく感じた違和感は、
『「動的平衡」という概念を最初に提唱したのは、ルドルフ・シェーンハイマーという科学者です。彼は、生命を構成する要素が絶えず入れ替わりながらも、全体として一定の状態を保つという考え方を実験的に示しました。福岡伸一氏が、この概念を拡張して「動的平衡」と名付け、生命を理解する上で重要な視点として広めました』
というWebの情報から明らかになりました。
偶々同じような違和感を感じた方のブログ記事「 ibaibabaibaiのサイエンスブログ 」を見つけたので参考になさってください。
ここからは私の私見ですが、「平衡」という概念は、わざわざ動的という形容動詞を付加しなくても、物質にせよエネルギーにせよ、すべてが動的に変化する中で、部分的にではなく全体的にそれらの事象を捉えたものではないかと思います。 言い換えれば、部分的に変化することがないために、全体としても変化しないという意味での「平衡」は、(現時点で)あり得ないということになります。
このような理解は、先のブログでも触れられているように生物に限ったことではなく、既に他の事物にも適用されています。 そして、もちろんそれはトランジションの考え方にも生かされています。
.png)